60cm水槽にぴったりのろ過装置を探していませんか?
水の透明度や魚の健康を保つうえで、フィルター選びはとても重要です。特に60cm水槽は中型サイズとして人気が高く、対応するろ過装置の種類も多いため、どれを選べばいいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「60cm水槽におすすめのろ過装置」をタイプ別に厳選してご紹介します。
上部式・外部式・外掛け式・底面式など、それぞれの特徴やメリット・デメリット、さらに口コミ評価やSNSで話題の製品まで徹底解説。自分の飼育スタイルや環境に合ったフィルターを見つけるためのヒントが詰まっています。
読み終わる頃には、あなたにぴったりのろ過装置がきっと見つかりますよ。
設置のしやすさやコスパ、メンテナンス性など、選び方のコツもあわせて紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
60cm水槽に最適なろ過装置とは?

なぜフィルター選びが重要なのか
60cm水槽は熱帯魚や金魚、小型エビの飼育に適した中型サイズの水槽です。飼育の自由度が高い一方で、水質の管理が安定するかどうかはフィルターの性能に大きく左右されます。
「でも、水換えしていれば大丈夫じゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、実際には水の透明度や魚の健康状態、水槽のニオイやコケの発生具合など、日常的なメンテナンスの手間を大きく左右するのがフィルターの力なのです。
特に60cm水槽では「ろ過能力」「ろ材の容量」「水流の強さ」「静音性」など、複数の要素がバランスよく備わっているかが重要になります。
60cm水槽に合うフィルターの条件
60cm水槽に対応するフィルターを選ぶ際にチェックすべきポイントは、主に次の5つです。
- 対応水量(フィルターの処理能力)
→ フィルターが対応する水量は「ろ過能力」に直結します。60cm水槽(約57L前後)に対応したモデルを選びましょう。 - ろ材容量(バクテリアの定着スペース)
→ ろ材が多いほど、水を長期的に安定させる力が高まります。 - 静音性(リビング設置なら特に大事)
→ ブーンという音が気になると設置を後悔しがち。レビューや口コミで静かさを確認しておくのがおすすめです。 - メンテナンスのしやすさ
→ 掃除の頻度やフィルター内部の洗浄しやすさも、長く使ううえで大きなポイントです。 - 設置スペースと見た目のバランス
→ フィルターの種類によっては、水槽内にスペースを取ったり、配管が目立つことも。水槽レイアウトとの相性を考えましょう。
「正直、何を優先したらいいか分からない…」という方も多いはず。
大丈夫、次のセクションで、各フィルターの特徴と違いをわかりやすく比べていきますよ。
ろ過装置の種類と特徴を比較

水槽用のろ過装置にはいくつかのタイプがあり、それぞれメリット・デメリットがあります。ここでは、60cm水槽に使われる代表的な4タイプのろ過装置について、特徴を比較してみましょう。
上部フィルター|手軽でメンテしやすい
上部フィルターはその名のとおり、水槽の上部に設置するタイプのろ過装置です。水をポンプでくみ上げて、フィルターに通してから水槽に戻すというシンプルな構造で、初心者でも扱いやすいのが特徴です。
メリット:
- ろ過槽が大きく、ろ材を自由にカスタムしやすい
- 水槽上に置くためメンテナンスが簡単
- 濾過力と価格のバランスが良く、コスパに優れる
デメリット:
- 見た目がややゴツくなりやすい
- フタの干渉や照明設置に注意が必要
「掃除がしやすいフィルターがいいな」という方には、上部式がぴったりです。
外部フィルター|本格的で高性能
外部フィルターは水槽の外に設置する密閉型のろ過装置で、本格的に水質を維持したい中級者〜上級者向けの方式です。密閉構造のためろ過効率が非常に高く、長期間安定した水質を保ちやすいのが魅力です。
メリット:
- ろ材容量が非常に多く、バクテリアの定着力が高い
- 静音性に優れ、インテリア性も高い
- 水槽内に機材がほとんど出ないので見た目がスッキリ
デメリット:
- 初期コストが高め
- ホースの取り回しや定期的な掃除に慣れが必要
「水質にとことんこだわりたい」「魚にとって快適な環境を維持したい」という方には最適です。
外掛けフィルター|省スペースで初心者向け
外掛けフィルターは、水槽の縁に引っかけて使うタイプのろ過装置です。コンパクトで設置も簡単なため、初めてのアクアリウムでもよく選ばれています。
メリット:
- 設置が非常に簡単、工具不要
- 比較的安価で入手しやすい
- メンテナンスもカートリッジ交換だけで済むものが多い
デメリット:
- ろ材容量は小さく、濾過力は控えめ
- カートリッジ式はランニングコストがやや高め
「まずはお試しで始めたい」「小型のろ過装置がいい」という方におすすめです。
底面フィルター|底砂を活かしたろ過方法
底面フィルターは水槽の底にろ過装置を敷いて、底砂を通して水をろ過するタイプです。底砂そのものをろ材として使う方式で、自然に近いろ過が可能になります。
メリット:
- 非常に広い面積でバクテリアを育成できる
- ランニングコストがほとんどかからない
- 水槽内にフィルターが目立たない
デメリット:
- 掃除しづらく、砂の厚さ管理が必要
- 初心者には設置や維持が少し難しい
「ナチュラル志向で底砂を活かしたい」「静かに長く運用したい」という人向けです。
どのフィルターも一長一短があるので、**「何を優先するか」**が選び方のポイントになります。次のセクションでは、具体的におすすめの商品をタイプ別にご紹介しますね。
60cm水槽におすすめのろ過装置【タイプ別】
上部フィルターのおすすめ機種3選
① GEX デュアルクリーンフリー DC-4560
60cm水槽にフィットするスリム設計の上部フィルター。ろ過槽が2段構造になっていて、物理ろ過+生物ろ過を同時に実現します。透明フタ付きで汚れの確認がしやすく、LEDライトとの干渉も少ないのが魅力です。
- 対応水槽:42〜60cm
- 流量:約8.5L/分
- メリット:メンテナンスが簡単・静音設計
- 価格帯:2,500〜3,000円前後(Amazon等)
- SNS紹介:アクア系YouTuber複数がレビュー済
「掃除の手間を減らしたいけど、しっかりろ過もしたい」という方におすすめ!
② コトブキ トリプルボックス600
コンパクトながら濾過力は強力な定番モデル。高さが約10cmとスリムなので、インテリア性も損ないません。自由にろ材をカスタマイズできるため、初心者から上級者まで幅広く使われています。
- 対応水槽:60cm前後
- 特徴:大容量ろ過ボックス・ろ材自由設置
- 静音性:非常に高く、レビューでの満足度も◎
- チャームでレビュー数200件超、☆4.5以上
「とりあえず上部式で失敗したくない」という方にピッタリです。
③ ジェックス グランデカスタム600
少し大きめですが、パワフルな濾過力を求める方にはぴったり。ろ過槽も広く、物理+生物+吸着ろ過まで対応できます。ろ材を多めに入れたい方に好まれるモデルです。
- 対応水槽:60cm
- 特徴:大型ろ過槽+優れたろ材循環
- メンテナンス性:上部開閉式でろ材交換がラク
「魚が多めだから濾過を強くしたい」「ろ材をしっかりカスタムしたい」という方におすすめです。
上部フィルターだけでも特性が異なるので、「静音・省スペース」か「パワフル・拡張性」かで選ぶのがコツです。
外部フィルターのおすすめ機種2選
① エーハイム クラシックフィルター 2213
外部フィルターの代名詞とも言える定番モデル。40年以上愛されているロングセラーで、「とにかく丈夫で信頼できる」という声が多く、長期運用にも向いています。無駄な機能を削ぎ落としたシンプル設計で、初心者にも扱いやすいのが特徴です。
- 対応水槽:〜60cm(約60Lまで)
- 流量:約440L/h
- ろ材容量:約3L
- メリット:静音性が高く、長寿命でメンテも簡単
- 価格帯:10,000〜13,000円前後(Amazon等)
- SNS紹介:多くのアクア系YouTuberが愛用・レビュー済
「まずは信頼できる外部フィルターを試したい」という方にぴったり!
② OASE フィルトスマート 60
ドイツの人気ブランド「OASE(オアゼ)」が展開する、コンパクト設計の外部フィルター。高い静音性と横置きも可能なデザイン性で、設置スペースに制限がある人にもおすすめ。プレフィルターも付属し、メンテナンス性も高いと評判です。
- 対応水槽:最大60L(60cm水槽までOK)
- ろ材:スポンジ+バイオろ材のセット構成
- 特徴:静音+横置き可+取っ手付きで移動もラク
- 価格帯:約13,000〜15,000円
- チャーム等で☆4.5〜5.0、SNSでも話題に
「静かで省スペースな外部式がいい」「デザイン性も重視したい」という方におすすめです。
水槽のろ過装置が決まったら、次に気になるのは「夏場の水温対策」ではないでしょうか?
👉【こちらの記事もおすすめ】【実は月○○円!?】水槽クーラーの電気代は意外と安い?エアコン併用や「いらない」判断の基準も解説!
本格的に水質管理をするなら、水温管理も同じくらい大切です。
👉【こちらの記事もおすすめ】【60cm水槽おすすめ比較】初心者から中級者向けまで!セット・単体・素材別に厳選紹介”
外掛けフィルターのおすすめ機種2選
① GEX 簡単ラクラクパワーフィルター MまたはL
その名のとおり、設置も掃除もとてもラクにできる外掛け式フィルター。60cm水槽にはMまたはLサイズが適しており、専用カートリッジの交換だけで簡単にろ過性能を維持できるのが人気のポイントです。
- 対応水槽:Mサイズ→約45〜60cm、Lサイズ→60cm以上にも可
- ろ過方式:3層式カートリッジ+バイオスポンジ
- 流量:毎時約300〜450L(モデルにより異なる)
- 特徴:静音設計+カートリッジ交換でお手入れ簡単
- 価格帯:1,800〜2,500円前後(Amazon・楽天)
- Amazonレビュー:☆4.0以上、初心者向けに高評価
「できるだけ簡単に管理したい」「コスパの良いフィルターを探してる」人にぴったりです。
② コトブキ プロフィットフィルター BIG
チャーム楽天市場店などでも☆5評価を得ている人気の外掛け式。ろ過スペースが大きめに設計されており、ろ材のカスタマイズもしやすいので、外掛け式ながら上級者のサブ機としても使われています。
- 対応水槽:60cm前後
- ろ過方式:物理・生物・化学ろ過対応
- 特徴:水流調節機能あり、濾過槽が広く高性能
- メンテナンス性:カートリッジ+自由ろ材両対応
- チャームレビュー:☆5(50件以上)
「見た目はシンプルがいいけど、濾過能力は妥協したくない」という人にぴったりです。
外掛けフィルターはとにかく省スペース・簡単設置・低価格が魅力です。「まず始めたい」「サブで使いたい」など、使い方次第で幅広く活用できますよ。
底面フィルターのおすすめ機種2選
① GEX マルチベースフィルター
底砂の下に設置して、水を砂利を通して吸い上げる構造の底面フィルター。シンプルな設計ながら、ろ材スペースをしっかり確保できて、長期的な水質の安定が期待できます。エアリフト式とパワーフィルター両対応。
- 対応水槽:30〜60cm対応(パネルを組み合わせて拡張可)
- 特徴:砂利をろ材代わりに使えるため経済的
- メリット:広いろ過面積+静音性が高い
- 必要条件:砂利厚2〜4cm必要、パワーフィルターと組み合わせ推奨
- チャーム・楽天で☆4.5以上
「ナチュラル志向で長く安定運用したい」「コストを抑えてろ過を強化したい」人におすすめです。
② ニッソー バイオフィルター60
長年愛されている底面フィルターのロングセラーモデル。底面全面をカバーするパネル式で、空気の力(エアリフト)で静かに水を循環させます。特に金魚やビーシュリンプとの相性が良く、底砂にしっかりバクテリアを定着させたい人に人気です。
- 対応水槽:60cm(規格サイズ)
- ろ過方式:エアリフト式(投げ込み式エアポンプ併用)
- 特徴:低価格・メンテナンス簡単
- 価格:1,000円台前半〜
- チャーム等で☆4.5以上多数
「とにかく静かに運用したい」「底砂を活かした飼育をしたい」人にはとてもおすすめです。
底面フィルターは設置こそ少し手間がありますが、ろ過面積が広くバクテリアの安定性が高いという点で、他方式にない強みがあります。
フィルター選びのポイントと注意点
60cm水槽に合ったフィルターを選ぶには、単に「人気商品を選ぶ」だけでなく、自分の水槽環境や目的に合っているかどうかをしっかり見極めることが大切です。
水流・ろ過能力の違いに注目
フィルターの「流量」は、ろ過力と直結する重要な要素です。
流量が多いほど水を循環させる力は強まりますが、「強すぎる水流」が苦手な魚種やレイアウト(たとえば水草水槽)では、かえってストレスの原因になることもあります。
「でも、強いろ過力の方がいいんじゃないの?」
たしかにそう思いがちですが、大事なのは**「適切なろ過力+穏やかな水流のバランス」**です。
たとえば外部フィルターであれば、流量を調整できるモデルを選ぶ、ディフューザーなどで水流を分散する工夫をするといった対策も考えましょう。
静音性やメンテナンスのしやすさ
ろ過装置は基本的に24時間稼働し続ける機器です。
とくにリビングや寝室など静かな空間に設置する場合、「音の静かさ」は非常に重要です。
- 外部フィルター → 高静音で運転音がほぼ無音
- 上部フィルター → 静かだが水音はややあり
- 外掛けフィルター → 機種により振動音あり
- 底面フィルター → エアポンプの音がポイント
また、メンテナンスのしやすさも大きなポイントです。ろ材の交換や内部の掃除が手間だと、ついサボりがちになりますよね。
「私も最初は面倒に感じていましたが、メンテが簡単なフィルターを選ぶことで、気づけば週1掃除が習慣にできましたよ。」
レイアウトや飼育魚との相性もチェック
ろ過装置によっては、水槽のスペースやレイアウトに影響を与える場合もあります。
- 外部フィルター → 配管が必要、インテリア性高い
- 上部フィルター → 水槽上部のスペースを使う
- 外掛けフィルター → 背面に張り出しができる
- 底面フィルター → 砂利レイアウトと相性◎
また、水流に弱い魚(ベタ、ネオンテトラ、小型エビなど)は、強すぎる水流を嫌がる傾向があります。フィルターの種類と魚種の相性も要チェックです。
選ぶときのコツは、「ろ過能力・音・見た目・手入れ」この4つをどれだけ重視するかをはっきりさせることです。それに応じて、自分にとってベストなろ過装置が見えてきますよ。
まとめ|60cm水槽のろ過装置選びで迷ったら
60cm水槽は中型水槽として人気が高く、対応するろ過装置の種類も豊富です。
その分「どれを選べばいいかわからない…」と迷ってしまうこともありますよね。
この記事では、上部・外部・外掛け・底面という4タイプのフィルターを紹介し、それぞれのおすすめ機種や選び方のポイントを詳しく解説してきました。
もう一度、選び方のポイントをおさらいすると、
- 手軽さ・掃除のしやすさを重視するなら → 上部フィルター(トリプルボックス600など)
- 水質の安定や濾過力を重視するなら → 外部フィルター(エーハイム2213など)
- コストや設置スペースを優先したいなら → 外掛けフィルター(GEX簡単ラクラクなど)
- ナチュラル志向で底砂を活かしたいなら → 底面フィルター(GEXマルチベースなど)
大切なのは、「どんな飼育スタイルを目指したいか」を明確にすること。
水流の強さ、静音性、見た目、メンテナンス性など、優先したい項目をはっきりさせることで、自分にとって本当に使いやすいフィルターが見えてきます。
「これでやっと決められそう!」
そんな気持ちになれたら、この記事がお役に立てた証拠です。
水槽のろ過装置は、あなたと大切な魚たちをつなぐ“ライフライン”。
ぴったりのフィルターを見つけて、快適でキレイなアクアリウムライフを楽しんでくださいね。

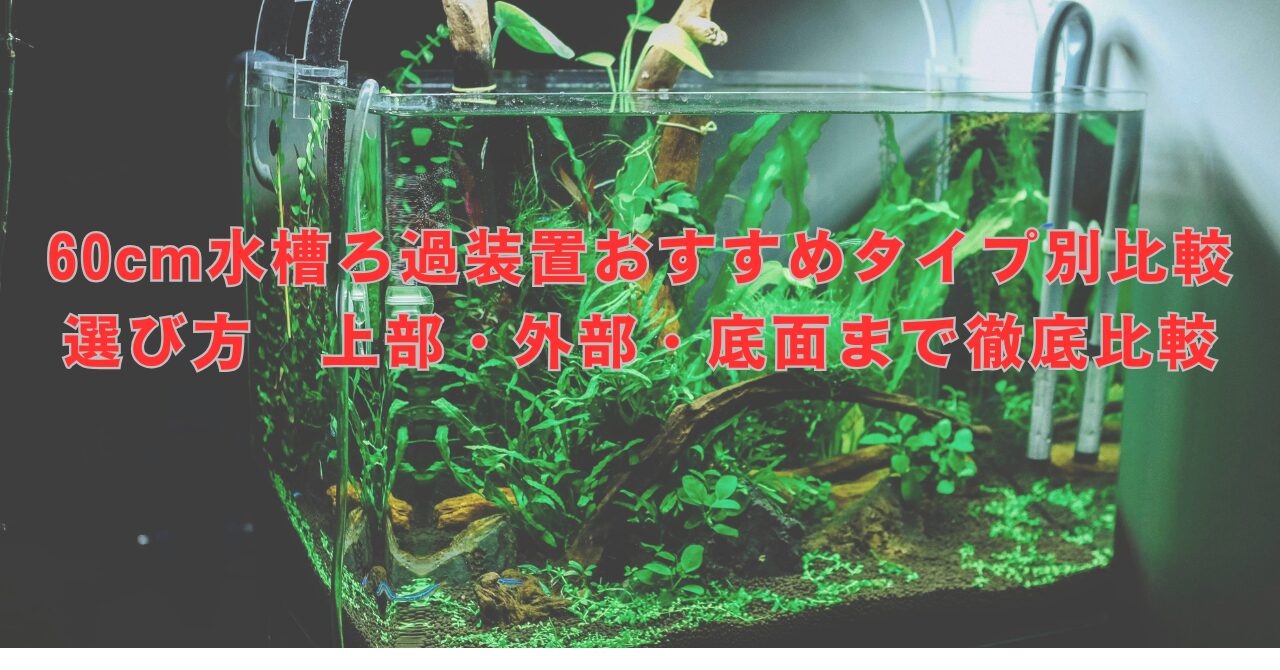











コメント